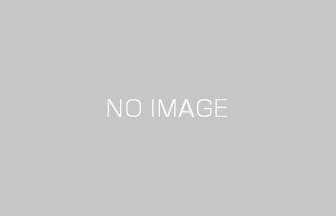今更ながら、ではあるのですが、『ウスケボーイズ』(河合香織著、小学館)を読みました。
深夜1時頃に読み始めて、さわりだけ読んで寝ようと思っていたのですが止まらなくなり、一気に読了。
ちょっと格好良く描かれすぎかな?とも思ったのですが、単に事実だけ抜き出しても、ドラマとして面白いのは間違いありません。
このドキュメンタリーの主人公となる「小布施ワイナリー」「ボーペイサージュ」「Kidoワイナリー」と、彼らのワインは結構飲んでいたので、なんとなく知った気になっていました。
まあ、それでじゅうぶんとも言えるのですが、映画化され今年2018年秋に公開されるということを知って、そう言えば読んでなかったやと思い出した次第。
いまや、リリースすれば即完売するような熱狂的な支持を得る彼らのワインが、どうやって生まれたのか。
周囲から無謀と言われ、ときに大事な人も失いながら、あくまで「自分のワイン」をつくる信念を貫き通す姿勢が綴られていきます。
個人的に好きなのは、曾我氏の弟の貴彦氏が、実家である小布施ワイナリーに戻りたいと言ってきたくだり。
兄で既に小布施ワイナリーを切り盛りしてきた彰彦氏は、その申し出を断ります。親から「なんで兄弟が仲良く一緒にやれないんだ!」という怒りを買いながらも、ワイン造りの際に遠慮が生まれ、判断に微妙にズレが出ることを恐れるのです。
今だからこそ言えることですが、結果としては正解でしたね。貴彦氏は北海道に移住し「ドメーヌ・タカヒコ」を立ち上げます。そして、日本では栽培・醸造が難しいと言われていた品種ピノ・ノワールに挑戦し、「ナナ・ツ・モリ」という銘ワインを生み出すことになります。
さて、個人的に「ウスケボーイズ」という言葉を知ったのは、勝沼で丸藤葡萄酒の大村さんを取材していたときのことでした。「ウツケ」と聞き間違えて、ずっと「バッドボーイズ」的な、あるいは織田信長的な、少々自虐が入った呼び名だと思いこんでいました。
業界の常識を無視して勝手なことばかりやっている、だからこそ革新的なことができたという意味で、曽我・岡本・木戸各氏らを表すには、それもありか?と、ふと思ったりもしたのですが…いや、やっぱり、いけません。
麻井宇介(あさい・うすけ)という人を、しっかり認識して記憶しておく必要があると思うのです。「ウスケボーイズ」というのは、彼に薫陶を受けた若き醸造家たちを意味するのです。
「海外の銘醸地にコンプレックスを感じながら日本でワインを造る時代は終わった。君たちは本気で海外に負けないワインを造りなさい」
日本のワイン造りを主導した醸造家・麻井氏は、余命宣告をされた身で若いワインの造り手に自分の遺した最後の言葉は、こんなことだったそう。
その言葉が発せられたワイン会は、2001年に行われたと言います。
いくつかの著作を残している麻井氏ですが、出色なのは『ワインづくりの思想』(中公新書)でしょう。これも2001年に上梓されています。本人の意図はどうかはわかりませんが、もはや日本でワイン造りに携わってきた第一人者の遺言の域にまで達しているような気がします。
それと同時に、21世紀のワイン造りの預言書とも思えるフシもあり、こんなすごい本が絶版になっているのが惜しまれます(Kindleでは読めますが)。
この本が面白いのは、銘醸地に対して、それが神から与えられた約束の地であるとでも言うような風土の運命論に疑問を呈したことです。例えばフランスのボルドーやブルゴーニュなど、ブドウ栽培に良い土地があったから素晴らしいワインができたのではなく、素晴らしいワインができたからこそ、良い土地だと言われるようになったのではないか、と。
その考えを発展させていくと、日本であったとしても、世界を凌駕する素晴らしいワインが造れるはずだということです。とくに20世紀後半は、技術革新や科学的な理解によって、何を良いワインとするかという考えの変化が、激しく移り変わっていた時代です。
麻井氏はフランスのワインに関して、「伝統産地では(変化が)模糊として見えにくい」(『ワインづくりの思想』プロローグ ― 銘醸地は動く)と書いています。
そう、革命や革新は、いつも辺境からやってくるのです。『西郷どん』が描いている明治維新が薩摩(鹿児島)という日本の端っこから生まれたことに限らず、料理に置き換えてもそうです。
スペインの『エル・ブリ』、イギリスの『ファットダック』、デンマークの『ノーマ』と21世紀初頭を象徴するレストランが、当時はガストロノミー大国ではない地から生まれています。
ただ、それをロマンチックに捉えすぎず、きちんと分析する聡明さも麻井氏は持ち合わせています。
「(伝統産地が)変化に遅れをとっているからではない。産地の厚みが格段に違うからだ。厚みには、規模の厚みと時間の厚みがある。そのどちらもが、当然のことながら、伝統産地は新興産地と較べ、圧倒的に勝っている」
要は、その規模と時間の厚みによって、例えば新しい風景を築く才能がいたとしても、埋もれてしまうのです。一方で辺境では、その新しさがくっきりと浮かび上がります。だから、影響力がかえって大きくなる、と。
そう言えば、以前、権威のある評論家の方から「君はなぜ、本物について触れようとしないのかね」と半ば非難されたことがありました。
その「本物」とは、言ってみればヨーロッパの料理のことです。
私の答えは、上記の麻井氏の言葉のなかにあります。
もちろん「本物」はリスペクトしています。ただ、ヨーロッパの「本物」でさえ変化していて、渦中にいるとその変化がかえって見えないことも多いと思うのです。
だとしたら、少し距離を取って、冷静に眺めることで見えてくるものもあるでしょうし、圧倒的な正解をお手本にして真似ていくのではなく、その土地らしさ、その人らしさを追求していくことも価値のあることだと思います。
『ウスケボーイズ 日本ワインの革命児たち』『ワインづくりの思想』の2冊を一気に読んで、アジアのレストランを巡ろうと決めた初心を思い起こさせてもらえました。
私は醸造家ではありませんが、この人がいてくれて良かった。
そう思える1人が、この麻井宇介氏です。